
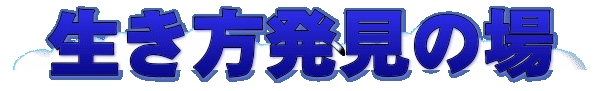
![]()
![]()
○〔商い〕に〔三法〕あり、〔三法〕とは〔始末する(無駄を省く)〕〔算用する(損をしない)〕〔才覚を働かせる(商機にはリスクを怖れずチャレンジする)〕ことである。(大阪商人)
○ 〔商人〕は、〔矢の下くぐれ(ここ一番の時は、リスクを取ることを怖れるな)〕。(江戸商人)
○ 〔儲からない〕のは、〔経営(商売)の仕方が当を得ていない(下手だ)からだ〕。(松下幸之助)
○ 食物等も上下無く、従業員を友達の如く思って稼ぐべし。(岩垣光定)
○ 〔手代いの仕損じ(従業員の失敗)〕は、〔主人の罪(経営者の責任)なり〕。(岩垣光定)
○ 〔成功する〕には、〔失敗の原因を己に求めることが大切である〕。(堤康次郎)
○ 人は、器量を見立てて(適材適所で)使うべし。(岩垣光定)
○ 主人に窮屈がられる家来あるは、めでたし。(岩垣光定)
○ 〔死に金〕は一切使わず、〔生きた金〕は惜しみなく使うことだ。(百瀬 結)
○ 〔金儲けする〕ことほど〔難しい〕ことはなく、〔損する〕ことほど〔易しい〕ことはない。(岩垣光定)
○ 金銀(お金)を望まぬ人はいないので、人と同じようにしていてはなかなか手に入らない、世上の人(大衆)と反対へ行くようにすべし(人の往く裏に道あり、花の山;もうはまだなり、まだはもうなり)。(岩垣光定)
○ 〔奢る〕とは、〔商人の分際に過ぎたる装い(生活)を成すを言う〕。(西川如見)
○ 始(創業者)中(二代目)終(三代目)の三拍子揃え(続け)ば、その後は数代続くものなり。(岩垣光定)
○ 〔息子〕は〔15、6歳までは奉公人同様にし〕、〔元服の後〕から〔息子の行作(扱い)〕をさせ、〔嫁を早く娶ってやる〕ことだ。(『分限玉の礎』)
○ 〔我より軽き処より迎えたる妻〕は、〔物事不足に思わず、愛想良ければ繁盛するものなり〕。(『民家分量記』)
| リ ン ク 先 |
| まるるサーチ |
| アクセスアップクラブ |
| Js ROOM |
| GAM NAVI |