
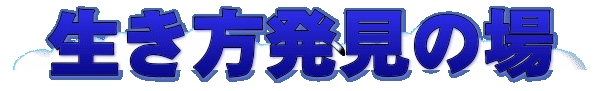
![]()
![]()
○〔問題を解決する〕には、〔問題の外に立って、問題の内に縮こまらぬことが大切である〕。(安岡正篤)
○ 〔本当の利〕とは、〔義をだんだんと実践して行くことによって成り立つ(義の和)〕。(安岡正篤)
○ 〔見識〕は、自分で修養工夫しなければ得られない。(安岡正篤)
○ 〔大政治の根本〕は、〔決断〕の二字にある。(金子得處)
○ 只思うことも無く為すことも無く、感に随いて動く時は我に象無し、象無き時は天下我に敵すべきもの無し。(『田舎荘子』)
○ 己れを忘れ物を忘れ、無物に帰す。(『田舎荘子』)
○ 生死の理に徹し、此の心偏曲無く、不疑不惑、才覚思慮を用いること無く、心気和平にして物無く、潭然(潭のように静かに澄みきった姿)として常ならば、変に応ずること自在なるべし。(『田舎荘子』)
○ 凡そ物形形象あるものは必ず対するもの有り、我が心に象なければ対するもの無し。(『田舎荘子』)
○ 心と象と共に忘れて、潭然(潭のように静かに澄みきった姿)として無事なる時は和して一なり。(『田舎荘子』)
○ 只自反して我に求むべし、師は其事を伝え其理を暁すのみ、其真を得ることは我にあり、これを〔自得;以心伝心;教外別伝〕と言う、師も伝うること能わざるを言うなり。(『田舎荘子』)
○
〔心の最も奥深い神(天理)〕によって、ものを見る。(安岡正篤)
○
国が滅びる徴候⇒(荀子『人妖論』)
◆
礼儀(秩序)修まらず、内外(国内と国外)別無く、男女淫乱にして、父子相疑えば、
○
己を修めないで人を指導しようと思っても、それは無理というものです。(安岡正篤)
○
〔妬心深き者〕は〔内争を生じ易し〕、〔与に交を結ぶべからず〕、また〔与に事を謀るべからず〕。(広瀬淡窓『自新録』)
○
〔医者〕というものは、〔患者を一目見て、この患者は危険だとか大丈夫だとか分かるようでなければいけない〕。(青山胤通)
○
〔本当の学問〕は、〔自分の身体で厳しく体験し実践するものであります〕。(安岡正篤)
○
〔学問〕は、〔体験〕を貴しとなし、その体験を〔錬磨する〕ことでなければなりません。(安岡正篤)
○一本の木を植えて、天が自分をしてこれを育てさせたと考られる、何故なら天はこの木を育てる汝を既に育てているからである(天然思想)。(安岡正篤)
○ 〔楊子〕は、〔天然思想〕に沈潜したのである。(安岡正篤)
○ 世人が一番確かなものと思っている〔肉体・物〕も、本来我が有ではない。(『列子 楊朱篇 』)
| リ ン ク 先 |
| まるるサーチ |
| アクセスアップクラブ |
| Js ROOM |
| GAM NAVI |