
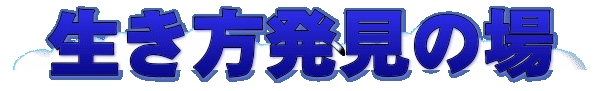
![]()
![]()
○クジラを仕留めるには、〔利刀〕よりも〔鈍刀〕の方が良い。(板倉綽山)
○ 困った時にうつむく者は役に立たず、困った時に仰向く者が役に立つのだ。(徳川吉宗)
○ 為すべき時は機を失することなくやってのけ、してはならない時にはどんなことがあってもしないことです。(板倉綽山)
○ 〔境遇・素質・使命を着実に生きて行く〕ことを、〔素行〕と言う。(林述斎)
○ 〔何をせずとも、ただその人がいるだけで何となく上下のものが安心する〕ということが、〔一番の達徳〕である。(安岡正篤)
○ 〔政治家〕は、〔情理(腹の底から納得すること)を尽くす〕ものでなければならない。(安岡正篤)
○ 〔政治家〕は、〔民衆に親しむもの(親身)であるべきである〕。(安岡正篤)
○ 〔政策〕が〔事件〕を支配せねばならぬ。(ナポレオン・ボナパルト)
○ 〔成る事多き〕も皆、〔身をはめて為す〕と〔逃げ足ながら為す〕との差より起こる。(林述斎)
○ 〔運〕とは、〔過去における積徳の作用に外ならぬ〕。(安岡正篤)
○ 〔上策、自治に在り(古来の名言)〕、〔真の善政〕とは〔下に在る者をして自ら善を成さしめるに在る〕。(安岡正篤)
○ 〔これが俺の仕事だ〕ということをやれ!(安岡正篤)
○ 〔真に活気ある世の中〕とは、〔20、30の者もどんどん相当の地位に登用せられて業績を発揮するし、60、70の者も世の重きに任じ、相交わって少しも可笑しくない〕ような世の中(例:幕末維新)でなければならぬ。(安岡正篤)
○ 〔病気をほっとく〕のは、〔中医に掛かっているようなもの〕である。(安岡正篤)
○ 〔人生を営む造化の働き〕を、〔内面的〕に見て〔文化〕と言い、〔外面的〕に見て〔文明〕と言う。(安岡正篤)
○ 〔理想を持った元気〕でなければならぬ。(安岡正篤)
○ 〔人物たる事の第一の条件〕は、〔理想を持つ〕ということである。(安岡正篤)
○ 〔修養〕とは、〔短所をそのままに長所にすることです〕。(安岡正篤)
○ 〔人物学を修める根本的・絶対的条件〕は〔私淑する人物を持ち、愛読書を持つ〕ことであり、その次には〔あらゆる人生の経験(艱難辛苦・喜怒哀楽・利害得失・栄枯盛衰)を嘗め尽くすことです〕。(安岡正篤)
○ 人間は、〔肚を据える〕と〔妙に落ち着く〕ものであり、〔落ち着く〕と〔物事がはっきりして来る〕。(安岡正篤)
○ 〔学問の真の目的〕は、人間の本質をよく把握し、これに随って本当の楽しみを得ることにある。(安岡正篤)
○ 「後姿が立派だ」と言われるようになれば、〔人間も出来た〕と言える。(安岡正篤)
| リ ン ク 先 |
| まるるサーチ |
| アクセスアップクラブ |
| Js ROOM |
| GAM NAVI |