
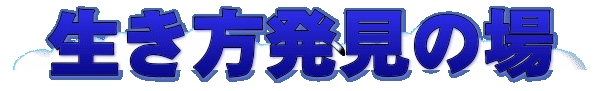
![]()
![]()
○〔<円>と成るには、<直線>は自らの進路を遮断せられて、無限にその方向を転ずるの極み遂に成る〕。(森 信三)
○
『礼記』にも〔四十にして仕う〕という言葉があるが、人間も四十までは修行(地に潜んで自己を磨くことに専念する)の時代だという訳です。(森 信三)
○ 学人はすべからく虚心坦懐なるべし、自己に一物を有する間は未だ真に他より学ぶ能わず。(森 信三)
○ 〔偉人の書物を繰り返し読むということ〕は、〔井戸水を繰り返し繰り返し汲み上げるにも似ています〕。(森 信三)
○ 一日読まざれば、一日衰える。(森 信三)
○ 〔偉大な実践家〕は、〔一般に大なる読書家であり、更には著述をもなし得る人が多い〕。(森 信三)
○ 人間が〔真に欲を捨てるということ〕は、〔自己を打ち越えた大欲の立場に立つということです〕。(森 信三)
○ 〔人間の価値〕は、〔この二度と無い人生の意義をいかほどまで自覚するか、その自覚の深さに比例する〕と言っても良いでしょう。(森 信三)
○ 〔教育の意義〕は、〔<立志>の一語に極まる〕と言っても良いほどです。(森 信三)
○ 〔真に偉大な人格〕は、〔その膝下を去って、初めてその偉大さに気付くものであります〕。(森 信三)
○
<イ音>は〔厳粛なる緊張感〕を示し、<ア音>は〔朗らか〕に、<エ音>は〔哀音〕を示す等々、これ皆〔言霊〕の不可思議なり。(森 信三)
○
〔真の教育者〕は、その人の内面より発する心の光の照らす限り、至る所に人材が林のように生い育って行くようでなくてはならぬでしょう。(森 信三)
○
〔真空(真我)に徹する〕ところ、〔個性の天真は自らにして躍り出ずるなり〕。(森 信三)
○
〔真の個性教育〕とは、〔相手をして真に止むに止まれぬ一道を歩ましめんとの一念に出ずるなり〕。(森 信三)
○
〔真に卓越せる師匠〕は、〔その愛する弟子には、最も厳しく対する〕と言うを得べし。(森 信三)
○
〔大声で生徒を叱らねばならぬということ〕は、それ自身〔その人の貫禄の足りない何よりの証拠です〕、〔真に偉大な人格であった〕なら、〔何も叱らずとも門弟達は心から悦服する筈であります〕。(森 信三)
○
〔優れた師匠〕というものは、〔常に門弟達(数歩遅れて来る者)を、共に道を歩む者として扱って、決して見下すということをしないものであります〕。(森 信三)
○
〔真に剛に徹しようとする〕なら、すべからく〔柔に徹すべきである〕。
○
〔人間〕は、〔自ら気付き、自ら克服した事柄〕のみが、〔自己を形作る支柱となります〕。(森 信三)
| リ ン ク 先 |
| まるるサーチ |
| アクセスアップクラブ |
| Js ROOM |
| GAM NAVI |