
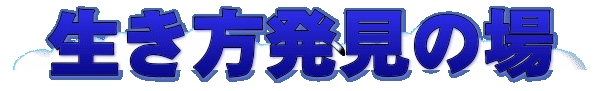
![]()
![]()
○〔窮すれば通ず〕で、精神(立志と人物如何)さえしっかりしていれば必ず運命は開ける。(安岡正篤)
○
六然⇒(崔銑)
◆ 自処超然(自ら処すること超然<物に囚われない>)
◆ 処人藹然(人に処すること藹然<相手を心地良くさせる>)
◆ 有事斬然(愚図愚図せず活き活きと)
◆ 無事澄然(水のように澄んでいる)
◆ 得意澹然(あっさりしている)
◆ 失意泰然(泰然自若としている)
○
六中観⇒(安岡正篤)
◆ 忙中閑あり(忙中の閑こそ本当の閑である)
◆ 苦中楽あり(苦中の楽こそ本当の楽である)
◆ 死中活あり(身を棄ててこそ浮かぶ瀬もあれ)
◆ 壷中天あり(自分だけの内面世界を持つ)
◆ 意中人あり(心中に偉人を崇拝する;人材の用意がある)
◆ 腹中書あり(哲学・信念がある)
○
人生の五計⇒(朱新仲;安岡正篤)
◆ 1.生計(養生法)
◆ 2.身計(社会生活の処し方)
◆ 3.家計(家庭の維持・家庭教育)
◆ 4.老計(いかに年をとるか)
◆ 5.死計(不朽不滅に生きる)
○
〔絶えざる思索と実践〕によって〔日々に新しい創造的生活をする〕ことを、〔立命〕と言う。(雲谷禅師)
○
〔人間生活の秘訣〕は、〔自分の精神を何ものかに集中すること〕です。(安岡正篤)
○
〔精神能力をある一つのことに集中する〕と〔霊感や機智が生ずる〕もので、そうすると〔驚くようなことが出来るものであります〕。(安岡正篤)
○
八観法⇒(東洋の人物観察法)
◆ 1、通ずれば、その礼するところを観る。
¶
順境の時に、何<金or女or地位or知識or技術>を尊重しているか。
◆ 2.貴ければ、その挙ぐるところを観る。
¶
登用する人物を観る。
◆ 3.富めば、その養うところを観る。
¶
金が出来た時、何を養い出すかを観る。
◆ 4.聴けば、その行なうところを観る。
¶
知行合一しているかを観る。
◆ 5.止まれば、その好むところを観る。
¶
板について(慣れて)来た時、その好むところを観る。
◆ 6.習えば、その言うところを観る。
¶
習熟した時、何を言うかを観る。
◆ 7.貧すれば、その受けざるところを観る。
¶
貧乏した時、何を欲しがるかを観る。
◆ 8.窮すれば、その為さざるところを観る。
¶
窮した時、何をするかを観る。
○ 六験法⇒(東洋の人物観察法)
◆ 1.之を喜ばしめて、以てその守を験す。
¶
喜んだ時、何をするかを観る。
◆ 2.之を楽しましめて、以てその僻を験す。
¶
楽しんだ時、何をするかを観る。
◆ 3.之を怒らしめて、以てその節を験す。
¶
怒った時、その節制力を観る。
◆ 4.之を懼れしめて、以てその独を験す。
¶
主体性を観る。
◆ 5.之を苦しましめて、以てその志を験す。
¶
苦しい時、その志の堅固さを観る。
◆ 6.之を哀しましめて、以てその人を験す。
¶
悲しい時、その人柄全体を観察する。
| リ ン ク 先 |
| まるるサーチ |
| アクセスアップクラブ |
| Js ROOM |
| GAM NAVI |