
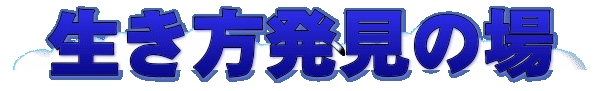
![]()
![]()
○〔健康〕は、〔第一の富である〕。(エマーソン)
○ 〔養生法の第一〕は、〔自分の身体を害うもの(<内から生ずる欲望(飲食の欲・好色の欲・睡眠の欲や七情の欲)>と<外からやって来る邪気(寒・暑・湿気・風)>)を除去することである〕。(貝原益軒)
○ 〔食べ過ぎない(腹八分)〕と、〔生まれつきの<内なる元気>を養って天寿を保つ〕。(貝原益軒)
○ 〔心〕は〔身体の主人〕であり〔平静〕を保たなければならないが、〔身体〕は〔心の下僕〕であり大いに〔労働〕させるべきである。(貝原益軒)
○ 〔養生の道〕は〔元気を保つ〕ことが根本であり、〔元気を保つ道〕は〔<元気を害するもの(内欲と外邪)を取り除く>ことと<元気を養う(飲食と動静に注意する)>ことである〕。(貝原益軒)
○ 〔人生の三つの楽しみ〕とは、〔善を楽しむこと〕〔健康で楽しむこと〕〔長く久しく楽しむこと〕である。(貝原益軒)
○ 〔養生の方法〕は、〔<勤むべきこと>をよく勤め、身体を動かし、気を巡らすこと〕である。(貝原益軒)
○ 〔養生の術〕は、〔心を静かにして身体を動かす〕にある。(貝原益軒)
○ 〔三欲を我慢せよ〕、〔飲食を節制し、色欲を慎み、睡眠を少なくする〕ことだ。(貝原益軒)
○ 〔言葉を慎む〕ことも、〔徳を養い身体を養う道である〕。(貝原益軒)
○ 〔養生の道〕は、〔<気まま(欲に負けて慎まないこと)>を押さえて、もっぱら<慎む>ことである〕、〔慎み(気ままの裏面)〕は〔畏れる(大事にする)〕ことが根本である。(貝原益軒)
○ 〔養生〕は、〔畏るる(大事にする)を以て本とする〕。(孫真人)
○ 人の〔身体〕は〔労働(動かす)〕すべし、〔労働(動かす)〕すれば〔穀気(穀物による気)〕が消えて〔血脈〕流通す。(華佗)
○ 〔養生の道〕に、〔久しく行き、久しく坐し、久しく臥し、久しく視る〕ことは禁物である。(『千金要方』)
○ 〔身体〕は大いに動かし労働することが良く、休養し過ぎてはいけない。(貝原益軒)
○ 〔初めに<快>なること〕は間違いなく〔後で<苦痛>となる〕、〔最初に努力して<自制>する〕と〔後ではきっと<楽しみ>となるものです〕。(貝原益軒)
○ 〔養生の大切な点〕は、〔<心>を<平静>にして気を和らげ、<寒・暑・湿気・風の外邪>を防ぎ、時々<身体を動かし>て食気の循環を良くすることです〕。(貝原益軒)
○ 何事も、〔忍ぶ〕と<災い>が無く、〔忍ばない〕と<不幸>になる。(貝原益軒)
○ 〔養生の道〕は、〔<怒りと欲>(最も<徳>を傷付けて<生>を害うもの)を忍ぶことである〕。(貝原益軒)
○ 〔養生の根本〕は、〔<楽しみ>を失わないことです〕。(貝原益軒)
○ 〔養生の四大要〕は、〔<内欲>を少なくし、<外邪>を防ぎ、<身体>を時々動かし、<睡眠>を少なくすることです〕。(貝原益軒)
○ 〔養生の四寡〕は、〔<思い>を少なくして心を養い、<欲>を少なくして精を養い、<飲食>を少なくして胃を養い、<言葉>を少なくして気を養う〕ことです。(貝原益軒)
○ 〔摂生の七養〕とは、〔言葉を少なくして内気を養うこと、色欲を戒めて精気を養うこと、味の濃いものを食べないで血気を養うこと、唾液を飲んで臓気を養うこと、怒りを制して肝気を養うこと、飲食を節制して胃気を養うこと、心配事を少なくして心気を養うこと〕です。(『寿親養老書』)
| リ ン ク 先 |
| まるるサーチ |
| アクセスアップクラブ |
| Js ROOM |
| GAM NAVI |