
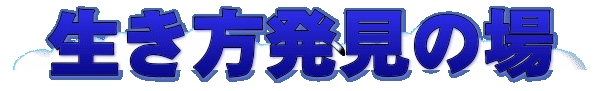
![]()
![]()
○〔開国の術〕は、〔譲道〕にある。(二宮尊徳)
○ 〔天分〕によって〔支出の度〕を定めることを〔分度〕と言う、〔分度〕を守らない限り世界中を領有したとしても不足を補うことは出来ない、〔分度と国家との関係〕は、〔土台石〕と〔家屋〕との関係のようなものだ、〔土台石〕があって初めて〔家屋〕が造営出来るのと同様に、〔分度〕を定めた上で初めて〔国家〕は経理出来る。(二宮尊徳)
○ 〔国や家が衰廃窮乏に陥る〕のは〔分内の財を散らしてしまうから〕だ、人が〔寒さに苦しむ〕のは〔全身の温かみを散らしてしまうから〕で、〔着物と重ねて体を被う〕とすぐに〔温かくなる〕、〔分度と国や家との関係〕は〔着物のようなもの〕だから、〔国や家の衰廃を興そうとする〕には先ず何よりも〔分度を立てる〕が良い、〔分度が立つ〕ならば〔分内の財が散らない〕から〔衰えた国も潰れかけた家も立てなおすことが出来る〕。(二宮尊徳)
○ 〔盛衰・貧富・豊凶〕を平均すると〔中正自然の数〕を得る、その〔中正自然の数〕に基づいて〔国や家の分度を立てるのだ〕。(二宮尊徳)
○ 〔国家の盛衰貧富〕は、〔分度を守るか失うかによって生ずる〕。(二宮尊徳)
○ 〔国家が衰貧に陥る〕と〔借財〕したり〔人民から絞り上げ〕たりして補うのが〔末世の通弊〕になっている、〔国君が分度を失って衰弱に陥り人民から絞り上げて富を得ようと思う〕のは、〔種を蒔かずに刈り取ろうとし、飯時になって米を買うようなもの〕で〔出来る筈が無い〕、そういう時は〔分度〕を守って貧民を恵み、荒地を拓くべきである。(二宮尊徳)
○ 〔政治教化が衰える〕と〔田畑が荒れ乱れる〕からその〔税収は次第に減じて足りなくなる〕、これが〔その国の病患〕である、〔その病患を救う法〕は、〔天分〕に従って〔国費を制限〕し、慎んで〔分度を守り〕、〔度外の財〕によって人民を恵み荒地を拓くことである。(二宮尊徳)
○ 〔国家の盛んな時(陽)〕を〔国政の基準〕にすると〔税額が増して人民が苦しむ〕、しかし〔国家の衰えた時(陰)〕を〔国政の基準〕にすると〔税額が減って君主が苦しむ〕、どちらも永安の道ではない、〔盛衰増減の税額を平均してその中間〕によって〔分度を立てる〕のだ、これこそ〔陰陽の釣り合った国家永安の基〕である。(二宮尊徳)
○ 〔荒地〕も〔借金〕も恐れるに足りないが〔足ごしらえ〕をすることが肝心である、〔足ごしらえ〕とは〔分度〕のことであり、〔分度〕が定まりさえすれば〔荒地〕をそれで拓け、〔借金〕はそれで償われ、〔衰えた国〕もそれで興せるのだ。(二宮尊徳)
○ 〔分度が確立する〕と、そこに〔分外の財〕が生ずる。(二宮尊徳)
○ 〔国君が分度を守る〕には〔自ら節倹する〕ことであり、そうすれば〔余財〕が生じ、〔仁沢〕が下に及んで人民は安堵し荒地が拓け田畑が良く整い税収は年々増してその国は必ず富むのである。(二宮尊徳)
○ 〔廃れた国を復興する〕には、〔国君〕が〔分度を守り経費を節約して、余財を差し出すべきである〕、そうしなければその衰廃を復興することは出来ないのだ。(二宮尊徳)
| リ ン ク 先 |
| まるるサーチ |
| アクセスアップクラブ |
| Js ROOM |
| GAM NAVI |